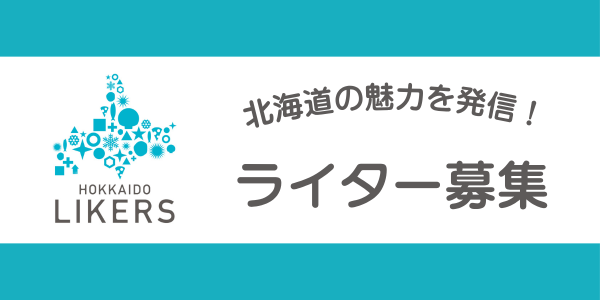【北海道宇宙サミット2022・全文掲載】自動車のEV化がロケットに関連!? 堀江氏らが語る日本の製造業の今とこれから(Session2)
“2040年の世界に開かれた北海道(HOKKAIDO)”をテーマにした特別連載「HOKKAIDO 2040」の特別編として、2022年9月29日に行われた、国内最大規模の宇宙ビジネスカンファレンス「北海道宇宙サミット2022」。現地約700人、オンライン約4000人の方が視聴したトークセッションでは、日本で宇宙に携わるフロントランナーが一堂に会し、様々な視点で議論が交わされました。
今回は、Session2「ものづくり大国 日本の再興!勝機は宇宙に」で語られた内容を全文掲載します。
Session1はこちらから登壇者
Our Stars株式会社 代表取締役社長 / インターステラテクノロジズ株式会社 ファウンダー 堀江 貴文氏
株式会社IHI/IHIエアロスペース 顧問 牧野 隆氏
株式会社釧路製作所 代表取締役社長 羽刕 洋氏
インターステラテクノロジズ株式会社 代表取締役社長 稲川 貴大氏(モデレーター)
はじめに

出典: ©北海道宇宙サミット2022
稲川氏:改めまして、インターステラテクノロジズ代表の稲川と申します。このセッション2は「ものづくり大国日本の再興!勝機は宇宙に」というテーマで、特にものづくり、製造業に焦点を当てながら宇宙の文脈で全体を話したいと思います。まず最初に登壇者の皆さんに自己紹介いただきます。
インターステラテクノロジズと私の自己紹介、我々として今どこまで進んでるか、そしてものづくり文脈で我々がどういう考え方をしているかを最初にお話させていただきます。私が代表の稲川です。(スライドに)鳥人間の写真を1枚載せているのは、10月からNHKの朝ドラで鳥人間がちょっと出まして、私が技術監修したので見てくださいというアピールです。帯広の航空学校が出てたりする飛行機のドラマが始まります。
最近はOurStarsという人工衛星の取り組みもやっていますが、主軸として宇宙ロケットをずっとやってきています。我々インターステラテクノロジズは、これまでMOMOというロケットの打ち上げをやってきました。昨年までに7号機までの打ち上げを行っています。昨年ですと、宇宙空間への到達を1ヶ月の間に2機成功するという、高頻度にロケットを打ち上げるという実績も作れたところです。
今、我々が開発に注力しているのはZEROです。役割としてMOMOの方は宇宙にタッチして戻ってくるような機体ですが、人工衛星を打ち上げるのがZEROという機体です。大きさとしても、長さが10m、直径50センチぐらいのMOMOに対して、ZEROは長さが25mぐらいで、重さにすると大体20倍から30倍弱と、一桁違うサイズ感のものです。大きさも役割も違うため、開発のハードルは1段階上がります。MOMOも継続的に打ち上げたいので、8号機、9号機の機体も実際に作っていますが、開発としてはZEROに注力しているというのが現状です。
Session1でも話に出ている通り、日本と世界の宇宙産業は非常に伸びています。ロケットの打ち上げ、そして人工衛星を宇宙に運ぶニーズが非常に増えているという話がありました。日本には既に種子島、内之浦から打ち上げられているH-IIAロケット、イプシロンロケットがありますが、世界のロケット打ち上げ回数として見ると、アメリカや中国が40回ぐらい年間で打ち上げているのに対して日本は3、4回。多くて6回ぐらいと、アメリカと中国に比べてロケットの打ち上げ回数がひと桁少ないのが事実です。こういった回数の違いもあって、日本で作られた人工衛星は、半分ぐらいが自国で打ち上げられていますが、半分ぐらいは海外に流出している状況です。急激に人工衛星のいろんなプレイヤーが出てきたことと役割が増えてきたこと、世界のロケットの選択肢も増えてきたことでこういう状況になっています。
日本のものづくりや日本の企業という文脈で言っても、バブル期と言われたような1990年代には世界の時価総額上位ランキングに日本企業がたくさんありました。企業の時価総額は本当に一面しか捉えられないもので、今後の期待値が先行する指標ではありますが、現在時価総額ランキングで上位にいる企業は、日本国内の企業で言うとトヨタ自動車さんとか、本当に限られたところになっています。
日本の企業への期待値が90年代から現在にかけて下がってきているのは事実だと思います。しかし、成長産業であると株価や時価総額が非常に伸びてきますので、今、成長産業である宇宙産業は日本の産業全体という文脈で考えてもまさに投資すべき分野だと思っています。
特に製造業で言うと、日本の製造業で今問題になっているのは、内燃機関だったエンジン車のエンジンがこれからどんどんEV化していくだろうということです。車の部品点数というのは従来は3万点ぐらいありましたが、これがEV化すると1万5000点とか2万点ぐらいに減っていきます。3万点の部品を作るだけのサプライチェーンが日本国内にあったわけですが、これが2万点となったときにどうなるかを考えると、大きな変革が求められるでしょう。
我々インターステラテクノロジズは今、多くの自動車関連会社さんと取り組みをさせてもらっています。人材出向の受け入れだとか、製造の発注だとか、いろいろと自動車関連会社とお話させていただくと、大変革の時代の中で、次の一手としてロケットや宇宙に注目してもらっていると感じています。
宇宙産業が伸びるということはこれまでさんざん言われていますが、もう少しベンチャーやスタートアップという文脈でお話します。ニュースペースや宇宙ベンチャーといわれるアメリカの企業では大きい時価総額がついています。一番大きいSpaceXという企業は、自動車会社のフォルクスワーゲンと時価総額ベースでは大体一緒ぐらいです。つまり超大手の自動車会社がここ10年、15年ぐらいで出てきているのがアメリカの宇宙産業の状況です。SpaceX以外も、いわゆるユニコーン企業と言われる、新しい企業だけれども大きな企業がもう10社近く生まれてきています。それに比べて日本はまだまだ小さい時価総額になっているのがリアルだと思います。
製造業は人手が必要になってくるので、雇用の文脈も非常に重要です。今、日本の宇宙産業の従事者は1万人ちょっとと言われています。今後きちんと宇宙産業を成長産業として取り込めればという仮定ですが、1万人ちょっとぐらいが10万人規模ぐらいの産業規模になるだろうと我々は考えています。もちろん市場としても、10倍以上に膨らんでくるだろうと、日本国内でうまくいけば30兆円ぐらい取り込めるんじゃないかと考えております。逆算して、これだけの人ってすぐいるんでしたっけ、移ってくれるんでしたっけと考えると、人材も非常に大きな論点になってくるかなと考えています。
登壇者紹介
稲川氏:今回のセッションの中で話したいところの背景を少しお話しましたが、最初にそれぞれパネリストの方々から簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。最初に堀江さんから簡単に自己紹介をよろしくお願いします。

出典: ©北海道宇宙サミット2022
堀江:はい、ロケットとかも作っているんですけど。ここでロケットの話をしてもしょうがない気もしますが。それ以外はパン屋さんをやったりだとか。
ロケットを造るまちづくりというのも実は結構重要だと思っていて、僕は、つくば万博の頃、1980年代に筑波研究学園都市を作ったときのエピソードをすごく覚えています。筑波の場所に研究学園都市をつくるということで、いろんな大学や研究機関を誘致してインフラを作ったは良いものの、人々が生活するという視点が全く欠けていて、ただそこに箱物があって、学生とか研究者を集めて「はい、どうぞ」みたいな感じにしたら心を病む人たちがたくさん出てきて。あるいは他にやることないんでっていう話なんですけど、筑波大学は学生結婚がめちゃくちゃ増えて。
結局、それを計画した人は「研究者が研究だけに、学生は勉強だけに集中する環境を作るべきだ」みたいな感じで作ったら、娯楽とかエンタメとか全くない街ができちゃって。みんな近くの水戸市まで飲みに出かけたりするようになって、結局居酒屋とかレストランとかエンタメ施設が後から作られたみたいなところがあって。全く計画的じゃなく、またガチャっとできてしまってるのが割と日本ぽいなみたいな感じがしていて。北海道の大樹町およびこの十勝地方は、ちゃんと人々が住んで生活が充実する街を作らないと人も来ないだろうなと思ったし、そこで働いてる人たちもすごく病んでしまうだろうなというふうに考えまして。
パン屋さんを作ったのも実はそれです。『小麦の奴隷』というパン屋さんは今全国に70店舗ぐらい開店してるんですが、主に過疎地区、人口5,400人ぐらいの町である北海道の大樹町で繁盛店を作り、それを全国にフランチャイズモデルで拡大している状況です。ぜひ時間があったら、北海道大樹町の本店まで行ってみてください。国道沿いのほんとにちっちゃなお店なんですけど。
それ以外にも北海道のテレビ局さんとのコラボ企画で『蝦夷マルシェ』という居酒屋を作ったり、そこの社長が『彗星に碧』というおしゃれなカフェ兼コワーキングスペースを作ったりとか。あとは、コスモールという道の駅があるんですが、最近そこで『堀江家』という家系ラーメンの店も始めました。うちのオンラインサロンの元気なメンバーがそこで起業して、家系ラーメンを作っています。先に断っておくと、そこのお店でスープを作ってるわけではなく、工場にレシピを渡して作ってもらって供給してもらってるので、ワンオペでできると。
地方はめちゃくちゃ人材不足で、特に若者の人材不足がすごく進んでるので、パン屋さんも石川県金沢市にある工場で冷凍生地を作って、各店舗に送って、店舗では整形して、調整して焼くだけという仕組みにして地方の人材不足にもちゃんと対応しています。モバイルオーダーやQRコードでのキャッシュレス化も対応しています。全然違う話のように見えて、食べ物屋さん、ご飯屋さん、そういった施設が増えていくことが町の発展にすごく大事であることを伝えたいと思っています。
もう一つ。大樹町には、何か工業団地とかを作って電力供給や道路などを政府の仕組みを使って整備してもらえると嬉しいかなと。逆に筑波研究学園都市みたいな構想を作ってほしいと思っています。
稲川氏:そうですね。まさに我々インターステラも今従業員100人規模になってきたところで、今後の採用計画としてももっと増やしていこうと思っています。これからもっと増えてくると、工場の拡張も含めて課題が出てきているのが今まさに堀江さんの話かなと思っています。
続いて株式会社IHIそしてIHIエアロスペース顧問の牧野さんより自己紹介をお願いいたします。
牧野氏:はい、牧野でございます。私は、簡単に言うと、小学生のときに1969年7月のアポロ11号の月着陸を中継で見て、それ以来「有人の宇宙船を作るぞ」と決めて、学生時代からもう45年ぐらい宇宙開発をやっています。宇宙船は行って帰ってくる乗り物なんですが、今の普通のロケットは片道切符で行っちゃうだけなんですよね。『宇宙戦艦ヤマト』は片道切符で出ていくようなもので乗り物ではないと、学生時代から設計する先生に鍛えられていたので、行って帰ることをやろうと固体ロケットが中心ですがいろいろとやってきました。
それとセットで、リエントリーで地球へ帰ってくるのも結構やってまして。はやぶさカプセルのチーフエンジニアをやっていました。大樹町でも1998年かな、ユーザーズというカプセルの落下試験をやりました。高度5キロに1トンぐらいのカプセルを上げてパラシュートの試験をしたんですが、それ以来、大樹町界隈の宿にトータルで3ヶ月ぐらい泊まったかな、というくらい大樹町にはよく来ています。
加えて、農地が広く飛び地もある十勝で十数年前から衛星データを使った農業サービスをやっている、今日も会場に来ている瀬下くんというスペースアグリ社の社長がいて、会うために帯広にも年に10回ぐらい来てました。そういう大好きな北海道に帰ってきています。ただ最初に言った通り、有人宇宙船を作ろうと言っているんですがまだ作れていないので「やり残しがいっぱいあるぞ」と思っている人生です。
現在、IHIエアロスペースで言いますと、イプシロンロケットの運用をやっています。『イプシロンS』を、科学国際競争力のある価格のロケットにして、年間4機、5機を打てるようになって、2号機以降IHIエアロスペースが打ち上げサービスをやることで今開発が進んでいます。
また来週、10月早々に予定されているイプシロンロケット6号機の打ち上げですが、ここにも民間の衛星、QPSさんのSAR衛星を搭載して打ち上げます。稲川さんの説明にもありましたが、我が国の衛星が上がるときに半分ぐらいしか日本国内で打ち上げられていない現状を変えなきゃいけないと。ニュースペース代表の稲川さんとオールドスペースを代表した牧野さんたちがいかにコラボできるかをこれから少し考えていこうと、これからも帯広エリアに来たいと思っております。以上です。
稲川氏:はい、ありがとうございます。牧野さんは、固体ロケットをまさに設計者として造ってきて、今は顧問になられましたがIHIエアロスペース社長として携わってきた第一人者としてのご発言だったと思います。続きまして釧路製作所の羽刕社長、お願いいたします。
羽刕氏:はい。下町ロケット、佃製作所、佃航平役阿部寛ならぬ釧路製作所の羽刕洋です。よろしくお願いいたします。弊社釧路市にありまして、帯広市、大樹町からは東に120キロいったところにあります。昭和31年に三菱系の湧別炭鉱という炭鉱が釧路市阿寒町にございまして、その子会社として設立されています。
設立当初は、その炭鉱内を走る気動車の整備であったり、炭鉱を掘削する設備のメンテナンスであったりからスタートしたわけですが、昭和38年に鋼製橋梁事業に乗り出しました。昭和45年に親会社が消滅しますが、三菱系の企業の資本を得て事業を独立いたしまして、現在は鋼製橋梁と鋼製タンクなどの動かない大型構造設備を作っている会社です。
この間に地域未来牽引企業、ISO認証、それから北海道働き方改革のシルバー認定、経産省から新・ダイバーシティ経営企業100選に選んでいただいております。
強みといたしましては、北海道の真ん中に日高山脈がありますが、東側にある橋梁メーカーが弊社のみでして、自社工場内で一貫生産ができることです。多くの技術者と品質保持をするためにISO9001をとったり、またこれからのロケット宇宙ビジネスへ向けて12月にGISQ9100も取得する予定です。
その大きな鋼構造物橋梁制作の経験と技術力を生かして、常に新しいことに挑戦し、着実に実行し実現していこうと考えて今事業を進めています。過去の成功事例としては、釧路市にある幣舞橋の高欄であったり、札幌市の菊水にある円形の歩道橋であったり、四国と本州を結ぶ番の洲にある高架橋であったりといった施工事例があります。また変わったところでは、札幌市にある北海道神宮の大鳥居であったり、釧路公立大学にある下田治先生の『幻想のオーラ』というモニュメントを施工させていただいております。
なぜ私がここにいるかというと、宇宙関連の構造物のお手伝いをさせていただいておりまして、2019年からロケットパートナーとしてインターステラテクノロジズ社にも出資をさせていただいております。
サイレンサーと呼ばれる地上設備、防音壁であったり、MOMOの3号機が初めて宇宙に到達する前に行われた縦吹き実験装置を納めさせていただきました。ここから120キロということでメンテナンスがすぐできるため、地の利を生かして宇宙関連の地上設備のお手伝いをさせていただいております。
これからZEROに向けてのロケットランチャーをインターステラテクノロジズ社および地元の高専と共同開発したり、昨年は経済産業省から事業再構築補助金を受けて精密機械設備を導入し、これからロケット部品の供給を始める準備をしています。
稲川氏:本当に大物から、そして今後は精密加工部品まで、もう既にいろいろ進んでいますね。
日本の製造業の現在地とは。強みと課題
稲川氏:ここで日本の製造業の現在地として、製造業の強みと課題を話題として出したいと思っています。最初に羽刕さんから北海道の文脈、課題も含めてお話いただければと思います。

出典: ©北海道宇宙サミット2022
羽刕氏:我々の地域で言いますと、基幹産業が漁業と水産加工、それから石炭、紙パが釧路にとっては大きな3つの産業でしたが、どれもこれもが現在は厳しい状況にあると認識しています。また昨今の少子高齢化という中で、特に地方は生産労働者が減っているという状況もありますし、人がいなくなる厳しい状況下です。ただ一方で、釧路地方にはその3つの基幹産業に関わってきた中小企業が多く点在しています。水産加工の技術であったり、石炭を掘削する技術であったり、紙パに関わる工場のメンテナンスの技術であったり、いろいろな中小企業があります。
我々も先ほどご紹介した通り、石炭から発生した会社でいろいろ変化しながら現在に至りますが、なかなか自分たちのやり方ややってきたことを変えて次のステップに踏み出せない中小企業の事業者がいるんじゃないかと思っています。我々はロケット産業に参画、参入する、そして実行して実現していくことで、地域のファーストペンギンになって、地域の事業が発展することで地域の企業と連携してさらにお手伝いできる方向に向ければいいのかなと考えています。
稲川氏:やはり重要なのがチャレンジ。新しいところに飛び込むことがものづくりとして重要だというお話ですね。牧野さんから日本の宇宙産業の文脈で、製造業の強みと課題をお話いただければと思います。
牧野氏:はい。日本という産業基盤が非常に広範なエリアに渡っているのはすごく大事なことなんです。ロケットと衛星両方とも安全保障上の問題もあるので、勝手に輸出ができないのと同時に、簡単に輸入もできないんですよね。そういう中で我々オールドスペースはいろんなものに国内の技術を使っていて、例えば、それこそ羽刕さんの会社にうちのランチャーを少し直したいと相談しに行ける、そういう企業の方必ずいてくれるという意味で、日本はやりやすいかと思います。
多分皆さんが感じているのは、インターフェースを切ったら向こうは知らないといったことはあまり言わない、日本のおせっかい文化みたいなのがあって。例えば羽刕さんにランチャーを作ってもらうと、きっと機体のことも心配してくれる、そういう関係になると思うんです。多分そういうインターフェースの向こう側も少し心配する、マニュアル通りに何かやればできるものじゃないときの、すり合わせ文化みたいなものが日本の企業と国民性になって、なんとなく今、僕たちも宇宙で仕事ができてるかなと思っています。
ただ先ほど稲川さんからもありましたように、段々儲かる仕事しかやらない会社が増えてきたりしてサプライチェーンが少し脆弱になってきているのが今の問題です。インターステラさんもそうですし、新しいスペースを含めて宇宙の産業規模を大きくしなきゃいけないときに、今が最後のチャンスだという感じもします。ニュースペースの方たちとオールドスペースが一緒になって事業規模を大きくしていくことが今の課題だと思っています。

出典: ©北海道宇宙サミット2022
稲川氏:本当にサプライチェーンが元々あるのは本当に日本の強みだと同時に、最後のチャンスという過激な言葉も出たところが印象的ですね。堀江さんからも日本の製造業という文脈、無ければ違う話を是非。
堀江氏:僕は、ロケット関連、それ以外でも製造業の人たちとお話をする機会があるんですが、結構ギリギリかなと思っていて。最近よく、円安になったから輸出が増えるとみんな言ってるんだけど、実は日本の国内ってGDPの大半は今内需なんですよ。サービス業が実はすごく多くて、日本の産業復興じゃないけど、GDPを上げていく方向性あるいは維持していく、下げないという話で言うと、みんな「経済発展だけが豊かさじゃないんだよ」と言うんだけど、やはり貧しい国は犯罪も多いしQOLも低いんです。経済が良くなって、僕は昭和47年生まれですけど、子どもの頃に比べるとめちゃくちゃ豊かですもん。僕が子どもの頃はうちの町にコンビニ1個しかなかったですけど、今はいっぱいありますからね。すごく便利になって豊かになったんです。それは経済発展なんです。
日本のGDPは内需が主体なんですが、これからは多分インバウンドで観光業が一つの柱になると思います。亡くなった安倍首相が実はすごく推進していて、多分10年ぐらい前、第2次安倍内閣のときに観光業をこれから日本の主力産業にするんだと言って、みんなポカンとしてたと思うんですけど、10年経ってコロナの直前2019年度に3,000万人を超える観光客が来ているんです。僕は1億を超えてもおかしくないと思っていて、一つは観光業だと思ってるんですね。
僕はもう一つの柱を宇宙産業にしたいと思っています。でも、先ほど僕が申した通りで、日本のサプライチェーンは今もう本当に瀕死、本当にギリギリのところで生きてるなと思いました。それは、実はバブルのときに産業が空洞化するようにどんどんオフショアに逃げていったんですよね。日本の人件費が高くなっちゃったから、もう日本じゃなくて海外でやろうと。サプライチェーン全体で外に行っちゃっている。部品メーカーさんとかも、例えば東南アジアに工場を作ったりとかして。日本は加工貿易の国だと教えられたと思いますけど、それって高度経済成長しているときぐらいの話で、僕が生きてた時代はどんどん日本から製造業がいなくなっている時代の話なんです。
宇宙産業をやってると、それをすごくひしひしとやばいと思うのは、ロケットは軍事転用ができるんです。衛星の代わりに爆弾を載せたらミサイルになるので非常に難しいんです。何が難しいかというと、ロケットにしか使われない、例えば、高精度のジャイロとかの部品が国内で調達できることが非常に大事。これは国内で調達できなくなると非常に難しい。韓国なんかは相当苦労していると思います。全部が全部手に入らないわけじゃないですけど、僕は結構難しい部分があると思います。
特に、例えば特殊鋼であったりとか。CO2の問題から、鉄鉱石の高炉を無くせという意見もありますが、高炉が無くなるとやばいんじゃないかなと僕は思っているんですよ。高炉から鉄を作って、銑鉄を作って、鉄鋼を作って、その後特殊鋼を作るわけです。日本の産業構造的な問題で、定年退職した技術者の人を、例えばポスコとか宝山鋼鉄とかが裏でものすごいキャラで引き抜いて技術流出していて、今、トヨタ自動車と日本製鉄がもめてたりするようなことが起こっている。こういったことを含めて待ったなしの状況になっているので、僕たちは宇宙開発をやって、ロケットに使われるような高度な製造メーカーさんを維持していく、サプライチェーンを維持していくっていうのは非常に大事なんじゃないかなと思いました。
実際、例えば、シールというターボポンプに非常に重要な部品を作っているイーグル工業さんというところに行ったですが、一部のシールを作るための素材が、「これは日本で作っていないんですよね」とか、IHIさんでも、一部「これは日本製じゃないんだよね」みたいな話を聞いているわけです。それは素材ですけどね。別に日本で作れないわけじゃないんだけど、需要が少ないから買い物してると。どんどん続けていくと、気づいたら日本で作れなくなっちゃっているということが起こるんです。これが、平時はいいんですけど、例えば、ロシアがウクライナに戦争を仕掛けましたみたいな話になると一気に来るわけです。例えば、ネオンという、ネオンサインとかに使われてる希ガスですが、工場がほとんどウクライナにあったりして。ウクライナからネオンが手に入らなくなるから、ネオンの工場を作らなきゃみたいな話になる。そんな難しいプラントではないですし、この辺の空気中にあるので圧縮すれば作れるんですけど、大規模な生産設備を作るのにどれぐらいリードタイムはかかるんですかという話になってしまう。割とマイナーな問題ではあるんだけれども、僕はやばいと思っていて。
あまりロケット関係ないですけど、例えば道路の舗装に使っているアスファルトがあります。アスファルトって何からできるんですか。原油からできるんです。原油からできるわけですから、例えばEVになってガソリンは使えません、プラゴミを削減するためにナフサを使えませんとなってくると、アスファルトはちょっと代替できないんじゃないですか、という話で。原油だけ引っ張ってきて、日本の精製プラントのオイルのサプライチェーンで、じゃあナフサはどうするんですか、捨てるんですか、みたいなことをトータルで考えないと多分駄目で。
例えば、僕たちのロケットだったらヘリウムをすごく使うんですよ。MOMOはそれこそ燃焼室に推進剤を送り込むのに直接的に使ってますし、ZEROでもコントロール用に使ったりとか最初のきっかけを作るのに使ったりとかするんですが、ヘリウムも本当に限られた油田とかガス田からしか噴出しないんです。それが枯渇するとどうなるんですかとか、戦争になったらどうなんですかみたいなことがあるという話です。
稲川氏:本当に材料の問題に結構直面していて。我々が開発をしていて頭を悩ませてると。
堀江氏:高いよね。高くなっているよね。
稲川氏:びっくりするぐらい値段が上がったりとか、そもそも数が入らないとか、大きな課題があるなと。
堀江氏:アルミもそうだよね。
稲川氏:そうですね、電気料金が上がると、アルミも上がりますね。
堀江氏:アルミは電気分解でしか作れないので。電力料金が上がるとアルミニウムの値段が爆上がりするんですよね。それでまた原発反対とか言っちゃうと、原発反対したら電気料金爆上がりするわけですよ。
稲川氏:課題という意味では、料金、金額という経済性の部分で課題としてあるなというところですね。
未来に向けて
稲川氏:これからもうちょっと未来の話をしたいと思います。最初に羽刕さんにお話を聞きたいんですが、これから日本が目指す方向で、特に人材面ですね。今の課題と解決策を教えていただけますでしょうか?
羽刕氏:地域の中小企業なので地域でどうするかっていう考えでお話をさせていただくと、先ほどいろいろな中小企業、ものづくり企業があるとお話したんですが、我々の地域で例えば機械工業界、鉄鋼業界の中で、企業の設備を共有しませんか、人材の能力を共有いたしませんかと。A社にこの機械があるのであれば、B社はその機械を持たないで借りましょうというように、設備の共有であったり人材の共有をすることで、1社ではできない仕事を3社ならできるんじゃないかという方向性を見出して、いろいろな仕事をこの道東地域で受けられるようにしたいと考えております。
それから我々の事業に将来参入してくる子どもたちをどう確保するかという点においては、弊社で持っているVRの溶接体験をする設備を活用して、学校でものづくりの楽しさであったり、溶接の楽しさを教える機会をいただいています。
またこの10月に弊社の工場内に溶接トレーニングセンターを作って、実際に溶接をしてゴミ箱とか、物を実際に加工して溶接の楽しさを教えることで将来の担い手になっていただく人材を何とか確保できないかと取り組みをしています。
稲川氏:究極の青田買いというところですね。本当に重要で、ものづくりは人づくりですとよく言われるんですが、こういう面も実際に取り組みされてるのは本当にすごいことだなと思って聞いていました。ここから牧野さんに、今後の目標みたいなところも含めて話しいただければと思います。
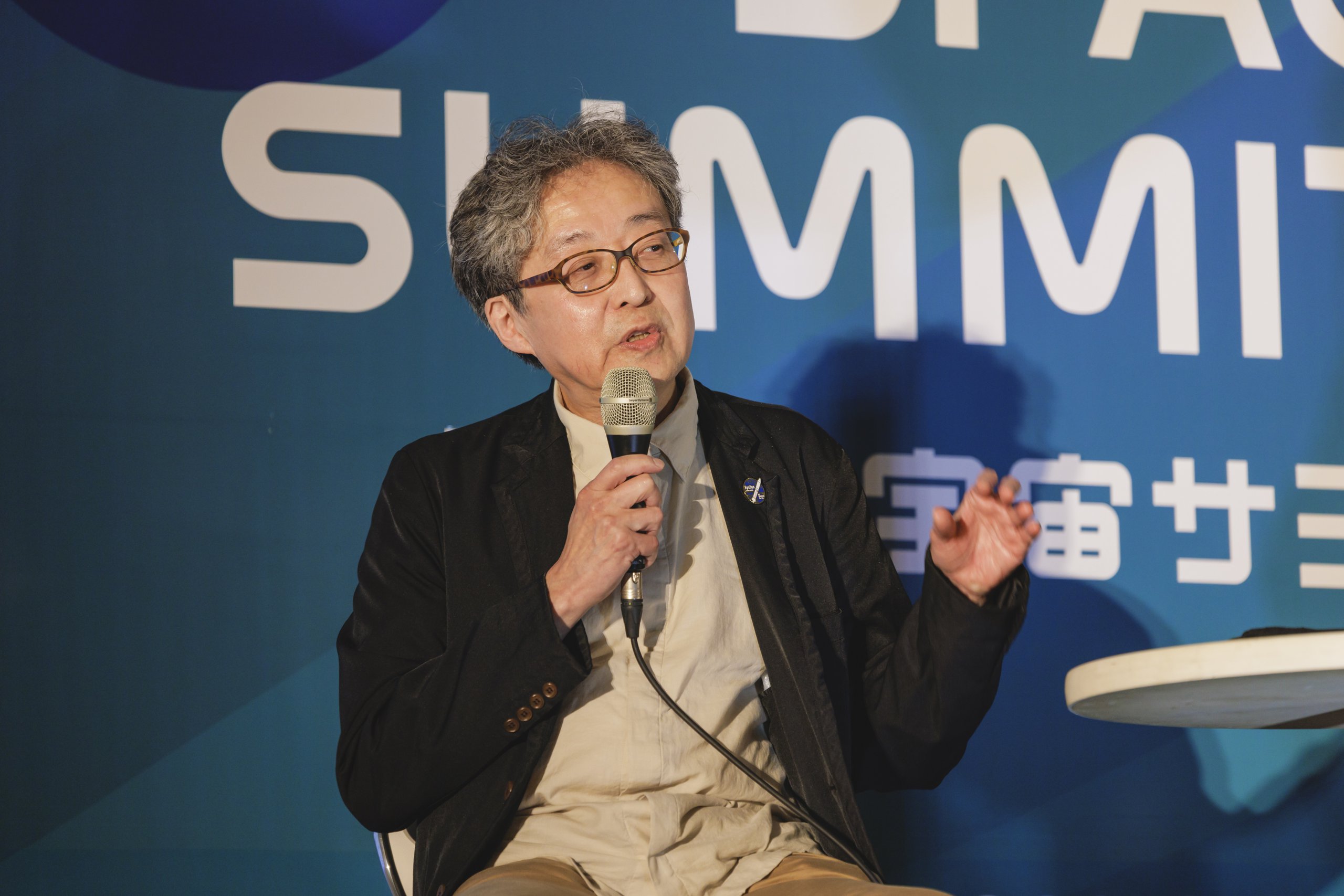
出典: ©北海道宇宙サミット2022
牧野氏:はい。宇宙というのはやっぱりグローバルに地球全体を見ることができるのが特徴で、最近IHIでやっていることをご紹介します。
経済性と地球環境保護を両立させるサステナブルな社会を目指して、住友林業さんのインドネシア圃場にマンゴーを植えるということをやっています。そろそろ実ができるので収穫に行かなきゃいけないのですが。
泥炭地の森林管理として、ヘイズ(煙害)と森林火災被害に対して、木をちゃんと育てていくことでCO2を固定することをやっていこうと、今いろいろ住友林業さんと検討を進めています。
また、宇宙から地上のデータをとるところで、明星電気でやっている『POTEKA????』という超高密度気象観測サービスを熱帯雨林用に変えて、地下水や水位を含めてコントロールしながら森林を育てていくことをやっています。CO2排出削減をネガティブエミッション(固定化)してCO2を減らすことに宇宙を利用していくのは我々宇宙人の究極の課題かなと思って取り組んでいます。
もう一つ大樹町絡みで、宇宙はいろんなビジネスがありますが、やはり観光旅行。例えば大樹町からスペースプレーンが飛んで戻ってくるとなると、大きなホテルも立ちますし、また宇宙に行くための訓練センターか何かを作ったりすると、実際に飛んで降りてくるビジネスよりも周辺の観光事業を大きく育てていかなきゃいけないと思っています。そういった中で、今IHIエアロスペースでも有翼実験機を作っています。実験は大樹町でやりたかったのですが、夏はHOSPOさんも忙しく貸してもらえないので、白老まで行って室工大の横の滑空場で試験をやっていました。まずは無人のスペースプレーンの実験機を作っていて、普通だとジェットエンジンだけで行って帰ってくるのですが、それだと宇宙っぽくないので、途中海の上で固体ロケットで加速して再び大樹町に戻ってくる試験を12月ぐらいにやりたいなと思っております。HOSPOさんに土日で直談判に行こうかと思っています。
稲川氏:非常に面白い話で、宇宙はカーボンニュートラルどころかゼロエミッション、ネガティブエミッションという地球環境に対しての問題解決になることは一般的に広く言われていたんですが、実際に住友林業さんそしてIHIという日本を代表する大手企業で動き出しているっていう話もエキサイティングだなと思いました。翼付きのロケット、スペースプレーンも、今日本として将来の宇宙輸送を担う次の宇宙機がどうなるのかは、我々含めてチャレンジ、そして競争してるような状況の中で具体的にもう製造もされて実験までしたいフェーズに進んでるものができていると。その実験場所として大樹が非常に重要だというところで、北海道スペースポートの盛り上がりと我々も緊張感持って聞いていたところです。
さいごに
稲川氏:最後に時間もちょうど来ているのでそれぞれお話いただきたいんですが、最初に堀江さんからロケットファンドについてお願いいたします。

出典: 北海道宇宙サミット2022
堀江氏:すいません宣伝です。今様々な資金調達等を行って、ロケットZEROを打ち上げるべく頑張っているんですが、なかなか銀行がお金を貸してくれないんですよ。昨日も某銀行さんに前夜祭でお会いして、お金貸してくださいと言ったら、華麗にスルーされました(笑)
でもそこは本当に言いたいんです。小説『日本興業銀行』という、高杉良さんが書いた本を読んでたんです。すごい時代だったなと。オイルのサプライチェーンを作ったときの話とか、元々高杉良さんは石油系の新聞か何かの記者さんだったので、めちゃくちゃ詳しくて。日本の戦後復興を成し遂げるために、アラビア石油とかから原油をタンカーで日本に運んできて、「日本にサプライチェーンを作るんだ」と意気込んで、そこに対して日本興業銀行はものすごい額の融資をするわけですよ。海の物とも山の物ともわからないものを初めて日本で作ることに対して銀行はこんなに金を出すんだと。いい時代だったんですね。ロケットはもう全然出してもらえません。マジで。政府系の、経済産業省さんから受託している案件とか、そういうものに対する紐付き融資はありますよ。でもそれはノーリスクじゃないですか。だからここに対して僕はすごく言いたくて。銀行の役割って何なんですかと。ベンチャー企業で、土地の担保の融資だったりするんですかと。東京に建てるマンションの土地とか建物に対して担保をつけて融資をするとかはできるんだけど、「工場を建てます」と、「頑張ってロケットを打ち上げます」と言ってるのに、ロケットが打ち上げるかどうかわからないからみたいな感じで一銭も出してくれないです。一銭も貸してくれないですよ。
だから僕はしょうがなくて、最近新しい制度で不動産クラウドファンディングができるようになったわけです。投資型クラウドファンディングに似てるんですけれども、これは不動産に対して小口で1万円とかそれぐらいから個人が投資ができると。今回はですね、年利5.5%ということで。本当に今は超低金利時代なので、銀行さんから借りるともっと安く借りられるはずなんですけれども。我々が家賃を払って大家さんになってもらうクラウドファンディングがありまして。これは応援型の不動産クラファンで、シーラという会社がやっている『利回りくん』というサービスです。昨日の工場見学ツアー(北海道宇宙サミットプログラム内)に来られた方、実際に第2工場を見ていただいたと思いますが、この『利回りくん』を組んで2日間でなんと3億円を集めさせていただいてやっております。
僕も小説『日本興業銀行』を読んで、こういうところに貸してくれる会社さんもあるんだと思ってちょっと感動してたんですけど、全然現実は違ったということで。しょうがないので、この『利回りくん』を使わせていただいて、今回は、圧力試験をやったりするための結構大きな建物「構造試験棟」というロケットの大きな燃料タンクを募集させていただきます。
実際には、これはクラウドファンディングで特典がございます。例えば、200万円以上を投資していただくと、工場にネームプレートが付くのに加えて、今流行りのNFTにも何か対応しているらしいです。
元本保証はないですが、一応我々の会社が存続する限りは利払いをしていくというか、家賃をお支払いします。区分所有の大家さんみたいなものです。例えば3,000万円以上をやっていただくと、ZEROの打ち上げ時に僕と一緒に、ほとんど人が入れない指令所で打ち上げを見学をしながらドキドキするやつとか、今はZEROはCGしかないんですが、このCGをグッドスマイルカンパニーさんという素晴らしいフィギュアメーカーさんにフィギュアにしていただいてプレゼントしたりとか、たくさん特典がありますので。『利回りくん』、ぜひ今のうちに登録してください。10月からこの構造試験棟を募集しますので、よろしくお願いします。あと、銀行さんも融資をよろしくお願いします。
稲川氏:こちらの詳細に関してはまた別途リリース出ると思いますし、チラシについてもこの会場内にありますので興味ある方はご覧いただければと思います。最後に羽刕さん、牧野さんに北海道宇宙サミットで残したいメッセージを一言いただければと思います。最初に羽刕さんから一言お願いいたします。
羽刕氏:本当にいろいろな能力を持った中小企業があると思うので、ぜひ挑戦する心を持って、新たな事業を見出してほしいと思います。昨今は国が中小企業を支援する制度がたくさんありますので、今堀江さんから銀行さんの話がありましたけども、銀行もぜひ中小企業に早い段階から寄り添って、一緒に助成金、補助金を入れる歩みを一緒にしていただくなどして、北海道にある、日本にある中小企業が宇宙事業をはじめいろんなビジネスでこれからも活躍できるようになってほしいなと思っております。
稲川氏:ありがとうございます。それでは牧野様、お願いします。
牧野氏:先ほども少しご説明しましたけど、なにせ平らで広いところがあるのは日本で北海道だけです。ちょっと冬は寒くて、十勝のダイヤモンドダストを見るようなときはもうしばれますが、すごくいい場所ですし、ぜひスペースポートや新しい宇宙をベースとして日本の宇宙産業の、観光の一番とんがった場所になってほしいと思っていますし、ぜひ少し協力できたらと思っています。
稲川氏:ありがとうございます。我々インターステラテクノロジズのロケット打ち上げだけではなく、サプライチェーン、そして他のIHIさん、IHIエアロスペースさんのようなこれまでロケット開発をしっかりやってきた企業からも、北海道スペースポートをすごく期待されている盛り上がりを感じていただければ、このセッションの意味があるかなと思います。
時間が過ぎてそろそろだというプレッシャーがありますので、ここで締めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
※本記事はカンファレンスでの発言を文字に起こしたものです。言い回し等編集の都合上変更している場合がございます。
連載「HOKKAIDO 2040」では、“2040年の世界に開かれた北海道(HOKKAIDO)”をテーマとして、大樹町を中心に盛り上がりを見せている宇宙産業関係者へインタビュー。宇宙利用によって変わる北海道の未来を広く発信します。連載記事一覧はこちらから。